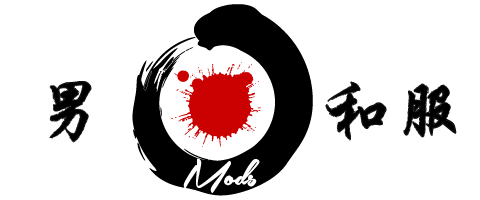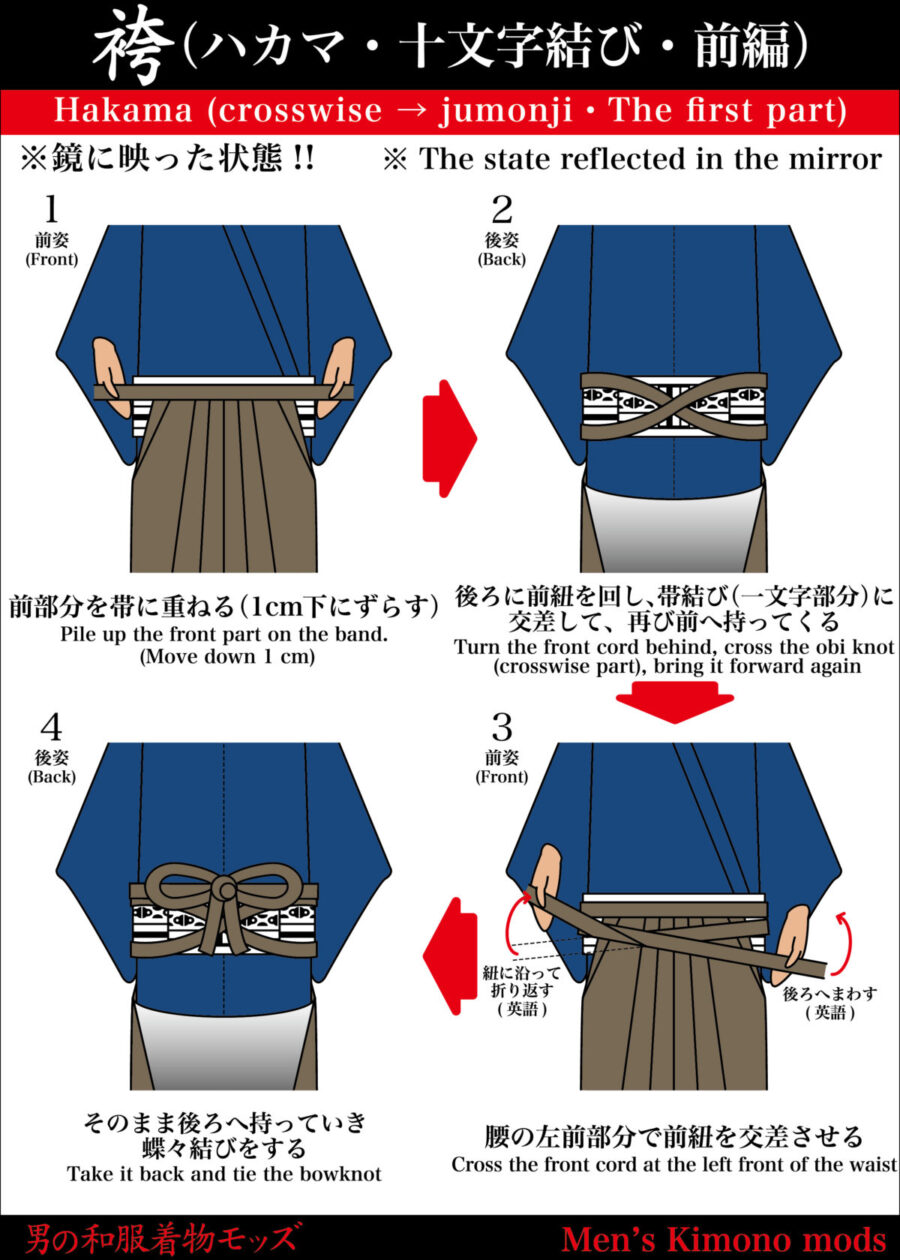
※こちらの記事は、和服ベースの服装(洋物MIX:和風80%以上、超洋物MIX:和風60%以上)に役立つ知識です。
男の和服着物ファンの方に人気の袴を特集していきます。
時代劇(戦国系、侍ゲーム系)などで和風に興味を持ったあなたは、袴(はかま)にも憧れをもっていますよね?
特に袴(はかま)は「男の和服着物の醍醐味」です。
和風コーディネートの幅が広がりますので、ぜひ身に着けてみましょう。
結論
・袴を取り入れると、ドレス感がコントロール出来ます。
・シーンに合わせて使い分けると、着物ライフがより楽しくなります。
・普段の袴の活用でより便利になります。
・袴の付け方をマスターしましょう。
ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

【メンズ着物寸法表(自動計算式)】
下をクリックすると着物寸法表に飛びます。(着物、長襦袢、羽織、袴)
身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。よろしければお使いください。
↓↓↓
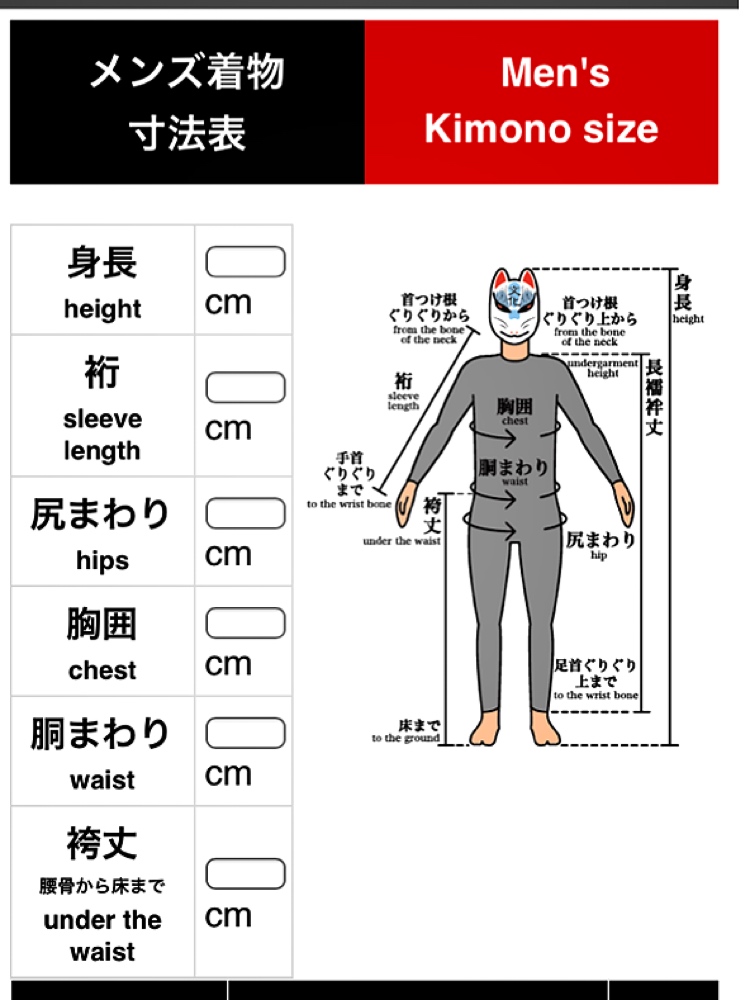
↑↑↑
上をクリックすると着物寸法表に飛びます。(着物、長襦袢、羽織、袴)
身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。
※注意
こちらの寸法はあくまで参考数値です。
正確にはお店の方にお尋ね下さい。
1. 袴(はかま)の種類
大きく分けると2つです。
馬乗り袴(うまのりばかま)

木綿の袴(はかま)です。大正時代の学生風。
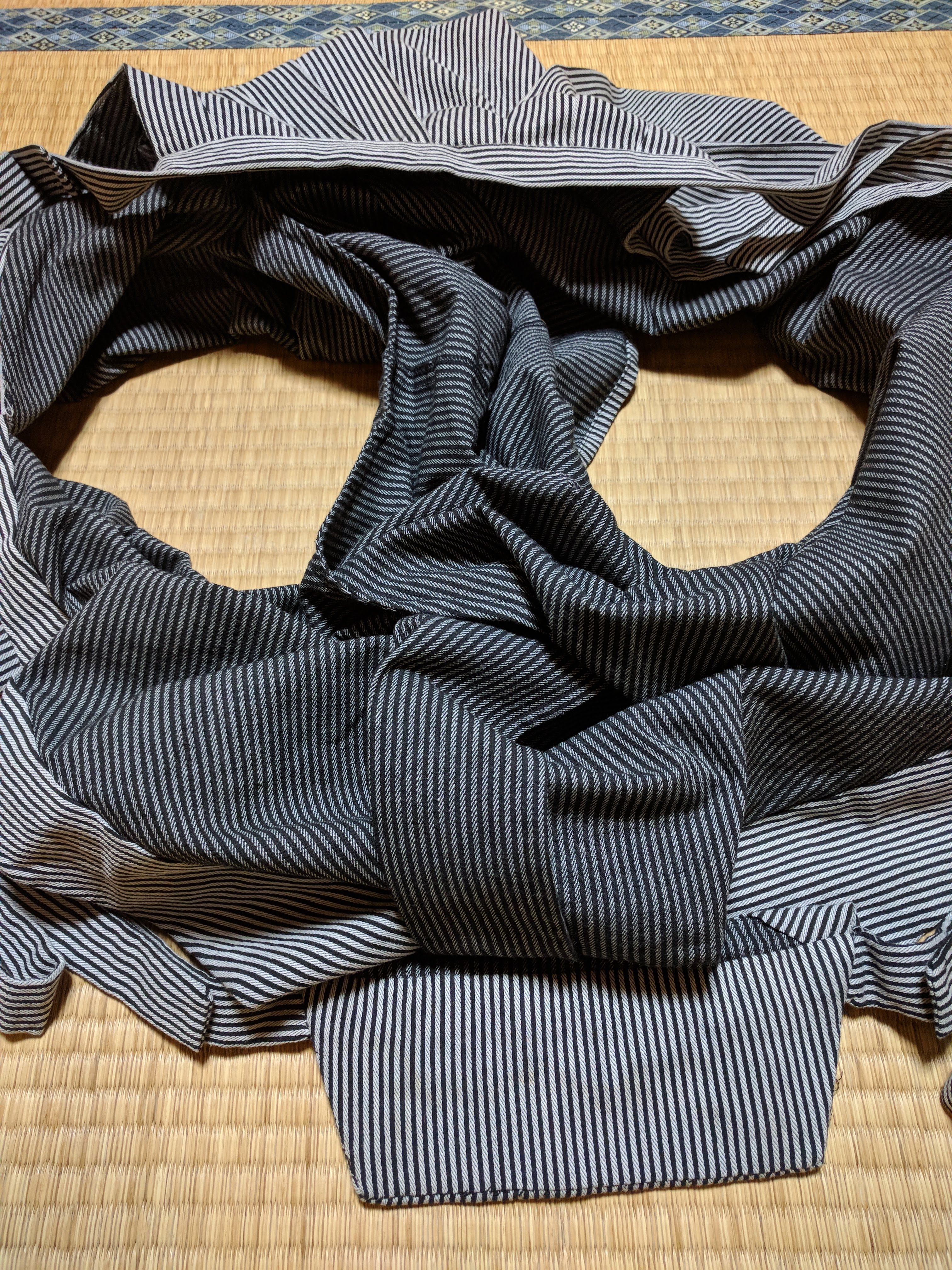
・二股に割れており、それぞれ足を入れる事が出来ます。
馬に乗りやすいよう設計されています。
一般的に侍スタイルで使うのはこちらです。
行灯袴(あんどんばかま)

御召地(おめし→光沢のあるドレッシーな生地)の袴(はかま)です。大正時代の女学生風。
t
・股がなく、筒状になっており女学生用に考案されました。
足を入れるパンツ風ではなく、ほぼスカート状です。
今は男性用のモノもあります。
格と用途
4つに分かれます
1.礼装用
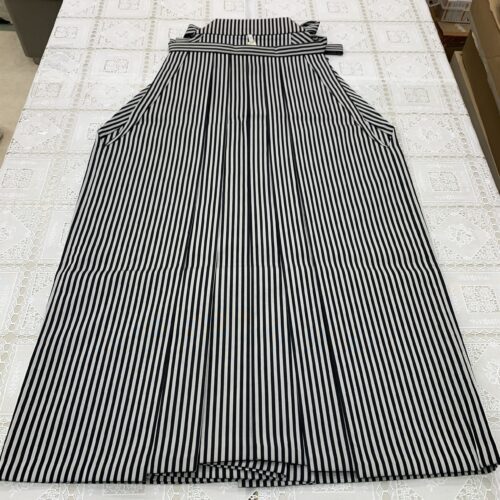
平袴(ひらばかま)で紋付に使う袴(はかま)で、生地は精好仙台平(せいごうせんだいひら)の縞模様です
2.舞踏用(ぶとうよう)

舞台用(芸能)の袴(はかま)です。
柄が派手で
相引(あいびき→袴の横、裾から脇明き止まりまでの長さ)部分が短くなっているのが特徴です。
3.お洒落用

形は礼装用と変わらず(平袴)素材が御召(おめし→表面に凹凸があり光沢感もある上品な生地)や紬(手で紡いだ糸を使ったカジュアル生地)系です。
4.普段着用

野袴(のばかま)と呼ばれるカジュアル袴(普段用)です。
例
軽衫(かるさん)

↑上の野袴は軽衫(かるさん)のデザインです。
武道袴(ぶどうばかま)

形
平袴(ひらばかま)

現在の裾が広がった形状の袴(はかま)。主に礼装・略礼装系です。
袴(はかま)は専用の生地で、密度が高く地厚です。
素材によってフォーマル度が変わります。(例えこの形状でも、木綿の物はカジュアルです)
※同じ平袴(ひらばかま)の仲間でも舞踏用の物は相引(裾から脇明き止まりまでの長さ)部分が短く、微妙に形が変わっています。
野袴(のばかま)

主に普段使い系です。
形は太いズボン状で動きやすく快適です。
素材は木綿などが多いようです。
最近は工夫されていて
チャックやポケットなどが付いている物も販売されています。
裁着袴(たっつけばかま)
(伊賀流忍者博物館 様より引用:
お相撲の土俵で掃除している人が着用しています。
足首が脚絆(きゃはん→足のスネを保護する布)でキュッとすぼまっています。
非常に動きやすいです。
江戸時代には伊賀忍者が着用したことから
通称、伊賀袴(いがばかま)です。
軽衫(かるさん)

イメージでは水戸黄門のような感じです。
裁着袴(たっつけばかま)ほど絞っていませんので
比較的現在の「ズボン」に近い印象です。
素材
フォーマル度高
精好仙台平(せいごうせんだいひら)

・仙台で生産される袴地です。↑今回は仙台平風の物になります。
⇧
御召(おめし→凹凸があり光沢感もある上品な生地)

・お茶席などでも使いやすい、略礼装向けです。
⇧
紬(手で紡いだ糸を使ったカジュアル生地)
(男着物.com様より引用:https://www.kimonosugata.info/sakuseirei_hakama.html)
・お洒落用で、ジーンズのような感覚です。
観劇や食事会などにも使えます。
特に無地の紬地はあると便利です。
木綿

・作業着として実用的な素材です。
フォーマル度低
色柄
フォーマル度高
グレーの縞模様

⇧
色無地(色は自由)
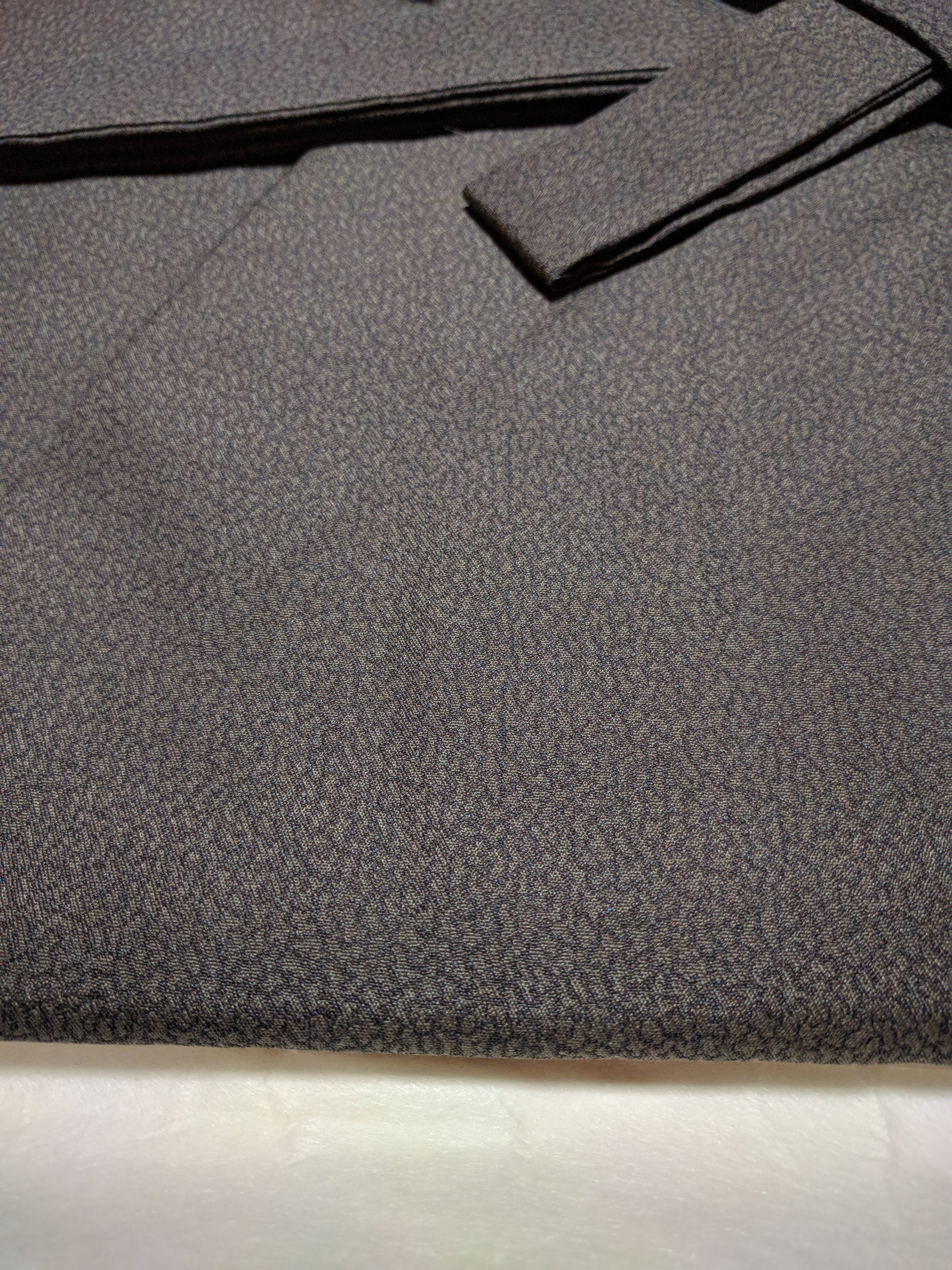
⇧
縞以外の柄
フォーマル度低
2.合わせ方
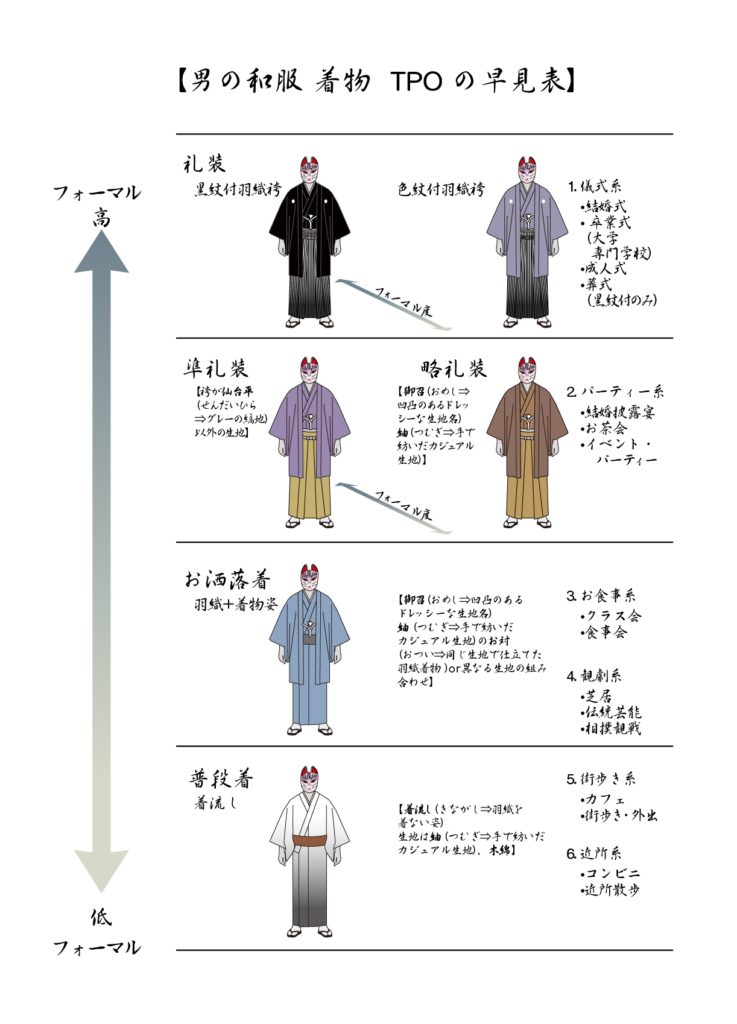
用途
礼装
長着

黒紋付き・色紋付きに
袴の種類
精好仙台平(せいごうせんだいひら)のグレーの縞模様

↑都合上、仙台平ではなく化繊の袴となります。
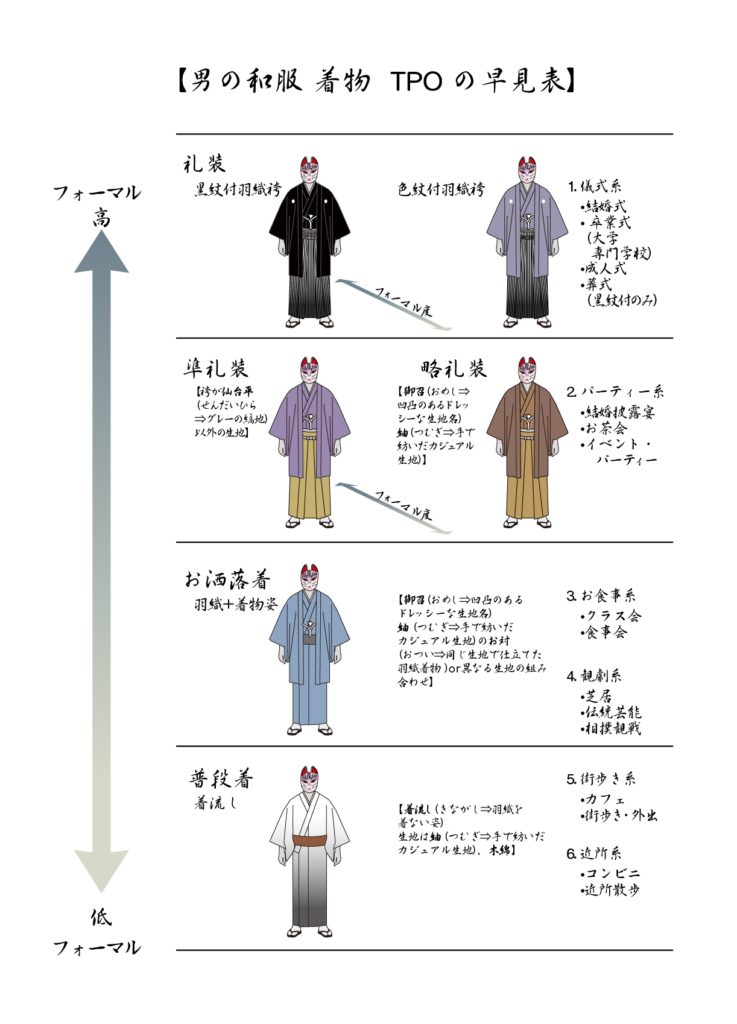
用途
略礼装
長着

色紋付きに
袴の種類
御召(おめし→凹凸があり光沢感もある上品な生地)の無地袴

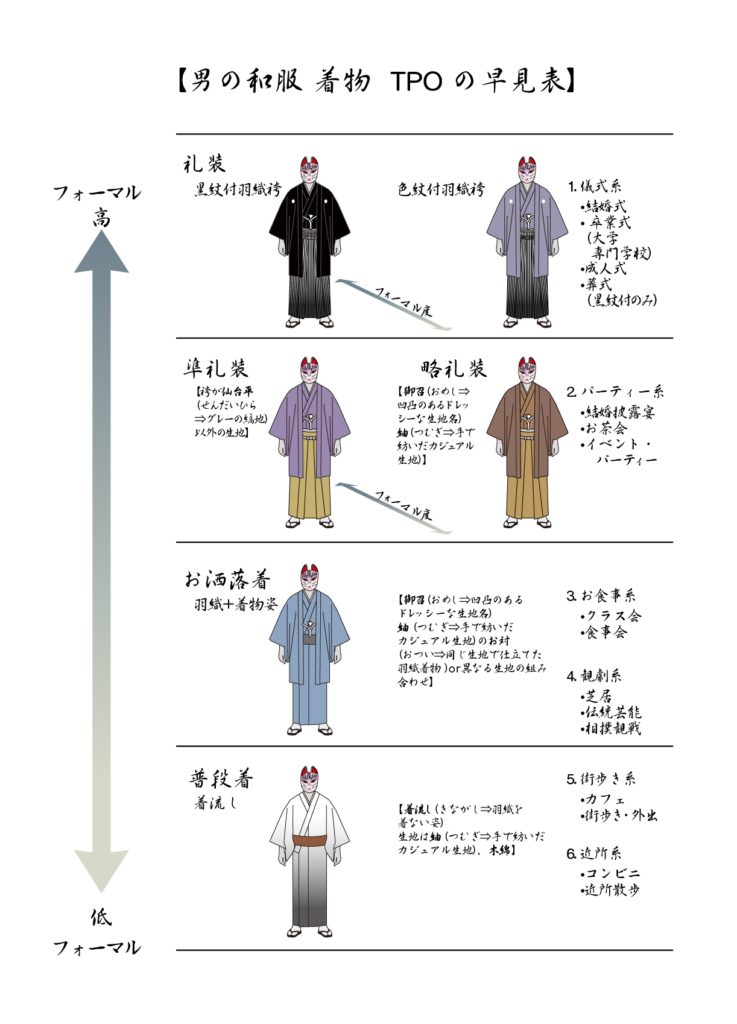
用途
お洒落用
長着

御召(おめし→凹凸があり光沢感もある上品な生地)、
紬(手で紡いだ糸を使ったカジュアル生地)の羽織+長着(ながぎ→着物の事)

袴の種類
御召(おめし→凹凸があり光沢感もある上品な生地)、紬(手で紡いだ糸を使ったカジュアル生地)の無地袴(縞も可)

同系色・トーンを合わせて
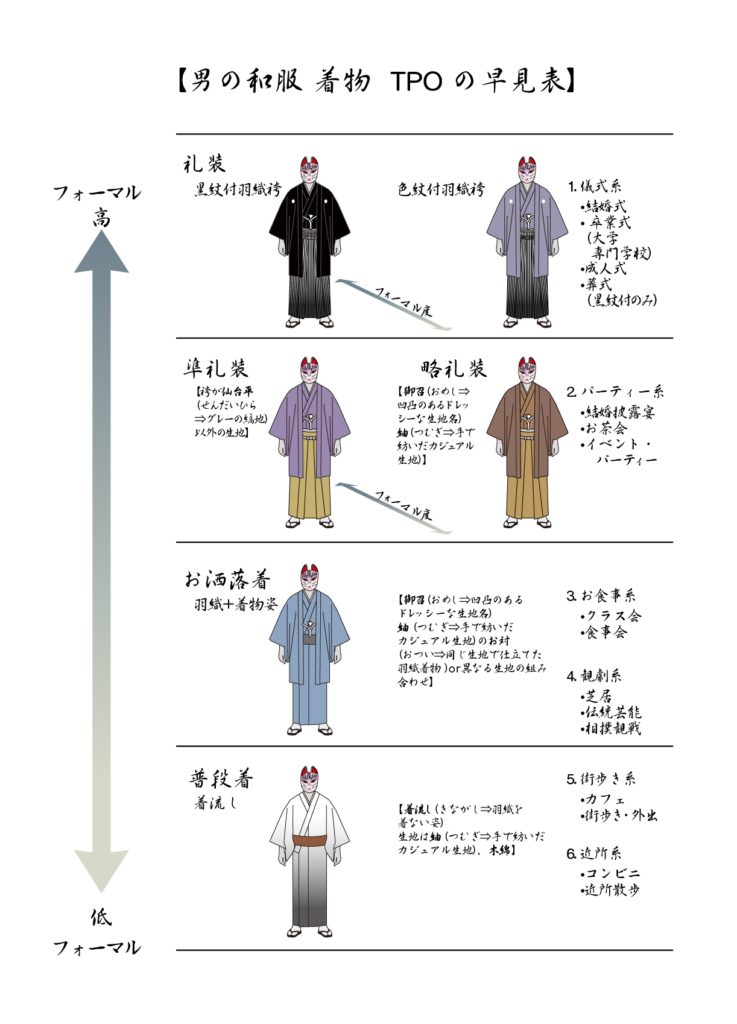
用途
普段着用
長着

紬、木綿の長着(ながぎ→着物の事)
袴の種類
紬(つむぎ→手で紡いだ糸で作るカジュアル生地)、木綿地の袴(はかま)
色合わせは自由
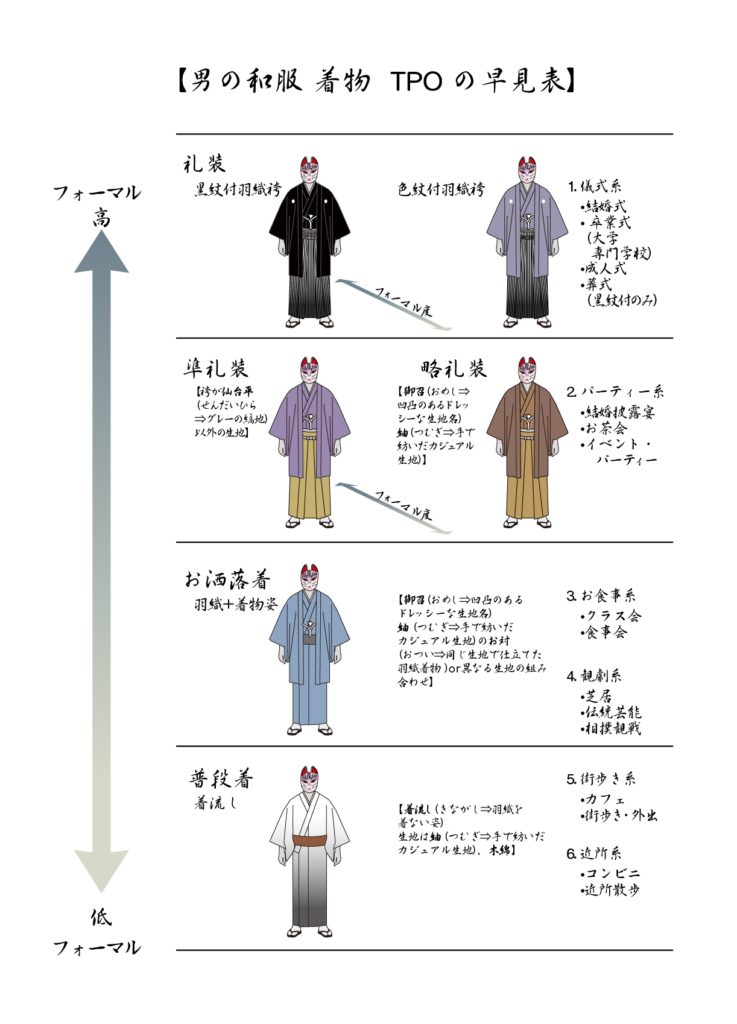
関連記事>>【男の和服着物の種類と格の見分け方】図解で解説!6つのシーン
3.袴の付け方
紐の結び手前までは皆同じです。
袴の付け方(前半)
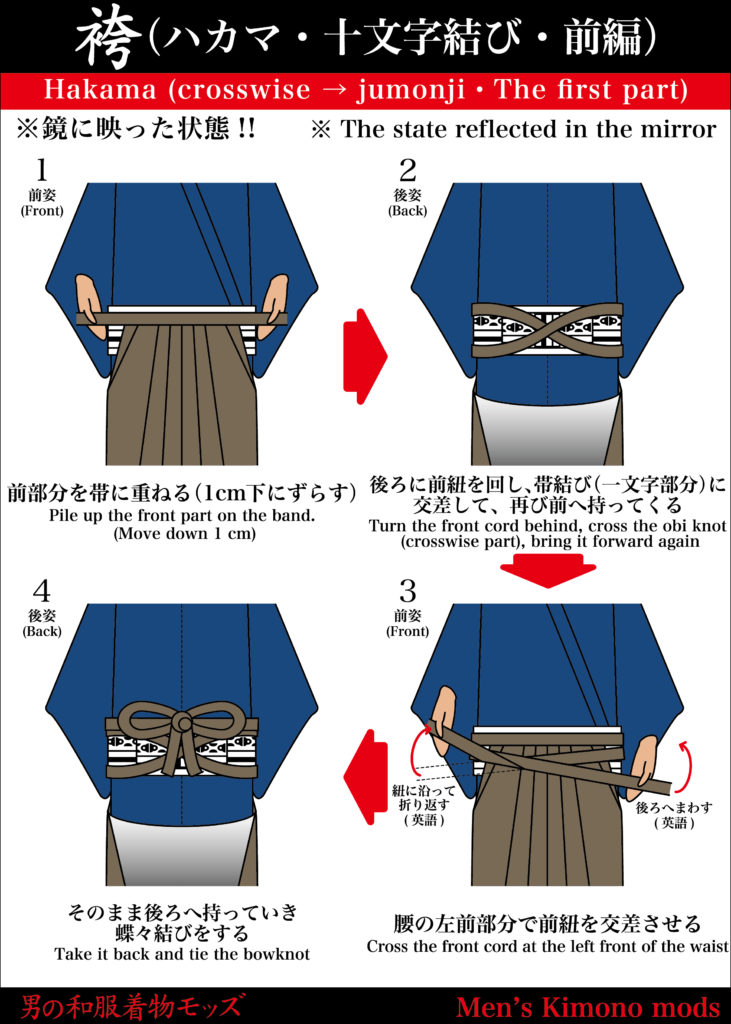
長着(ながぎ)を着て帯を一文字(いちもんじ→一の字に結ぶ事)に結んでおきます
⇩



長着の裾端を持って、後の帯に端折って折り込みます
⇩


端折った周辺をキレイにたたみます
袴に足を入れられるように開いておきます
※男性用として殆ど馬乗り袴(うまのりばかま→ズボン型)が主流ですが、今回は行灯袴(あんどんばかま→スカート型)になっております。
⇩


前紐をあてます
⇩

前紐を後の帯結びに交差するようにしめる
⇩

紐を右脇で交差させます
⇩



下側の紐を折り返します
⇩

折り返した紐は前の紐と重ねます
⇩

後で紐を結びます
⇩

袴の腰にあるヘラを帯に差し込みます
⇩

腰板(こしいた)をしっかり腰に密着させます
⇩
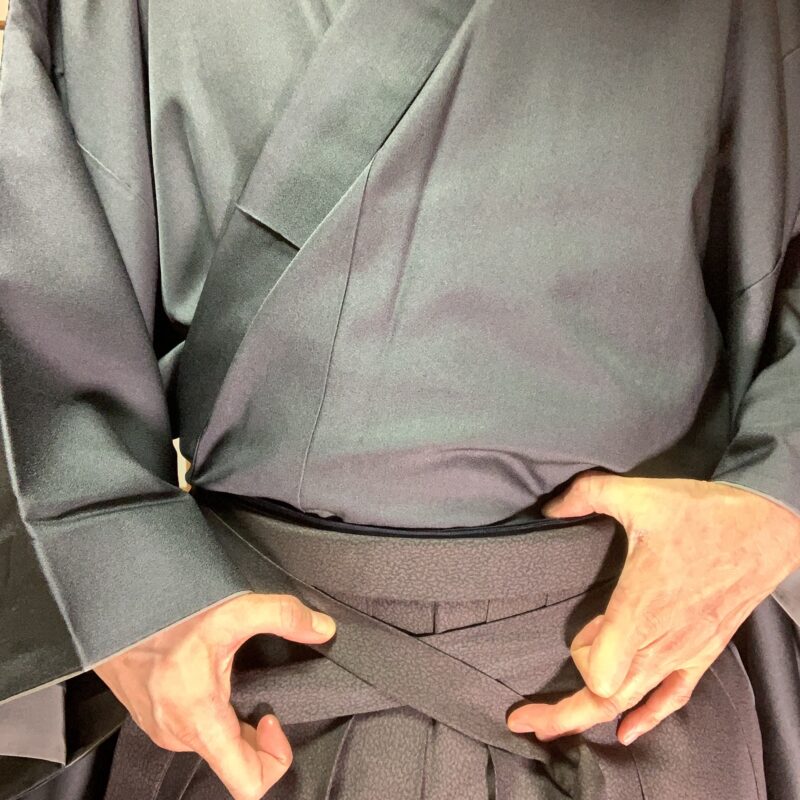
後ろ紐を前に持って行きます
⇩
前で後ろ紐を結びます
袴の付け方(後半)
横十文字結び

・一般的な結び方です。礼装に結びます。
左右の紐を重ねます(右紐が上)
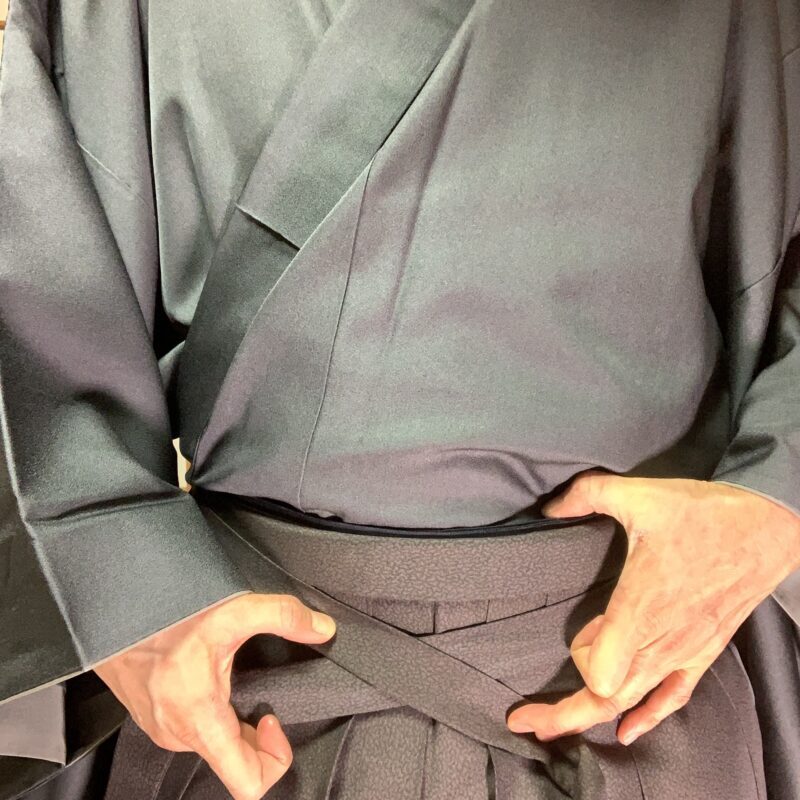
⇩

このまま前紐の下に入れ込みます(今回は上から入れてます)
⇩
重ねた下側を真上に上げて、巻き付けていきます

⇩
もう一方の紐を7~8cm幅に折りたたみます

⇩
たたんだ紐を正面中央に置きます
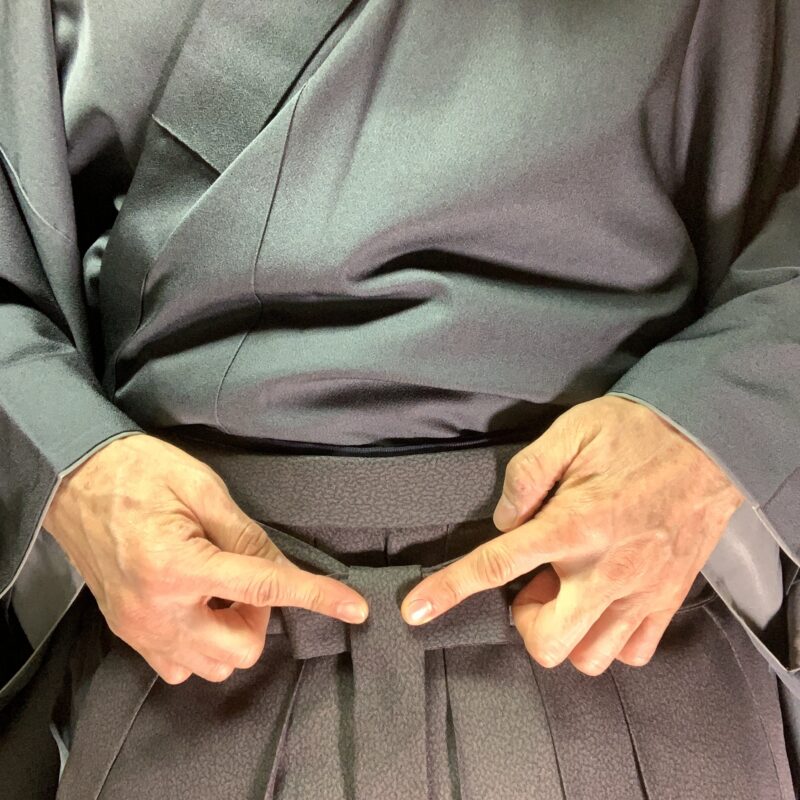
⇩
下からたたんだ部分を巻き付けるようにします

⇩
巻き付けている紐の残りが20cm位になったら、横十字の形にします
上と下それぞれ2~3cm出るようにします

横一文字結び
・変形型です。普段でも改まった時でも大丈夫です。(お茶などでも使われます)
帯結び前までは、横十文字(よこじゅうもんじ)の方法と同じです。
下の紐を畳んだ紐の中央にどんどんまいていきます。



⇩
下に余った紐を横に持ち上げて、袴の前紐の下に重ね始末します。


⇩
一文字になった結びが左右対称に整えて完成です。
結び切り(駒結び)
・簡易型です。野袴(のばかま)などには良いと思います。

後紐の左右を前で交差させます
⇩

左紐をからげ、下から引き揚げます
⇩

右の紐を上から下へおろします
⇩

おろした右の紐を袴紐の下から上に通します
⇩

紐を全部上にひきあげます
⇩

上下の紐を交差させて結びます
⇩

紐を左右に引き結び切ります
⇩

余った紐の残りは両脇の紐にからげて隠します
袴の畳み方


関連記事>>【男の和服着物の簡単な畳み方】時間ない方必見!プロ御用達の2種類
【メンズ着物寸法表(自動計算式)】
下をクリックすると着物寸法表に飛びます。(着物、長襦袢、羽織、袴)
身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。よろしければお使いください。
↓↓↓
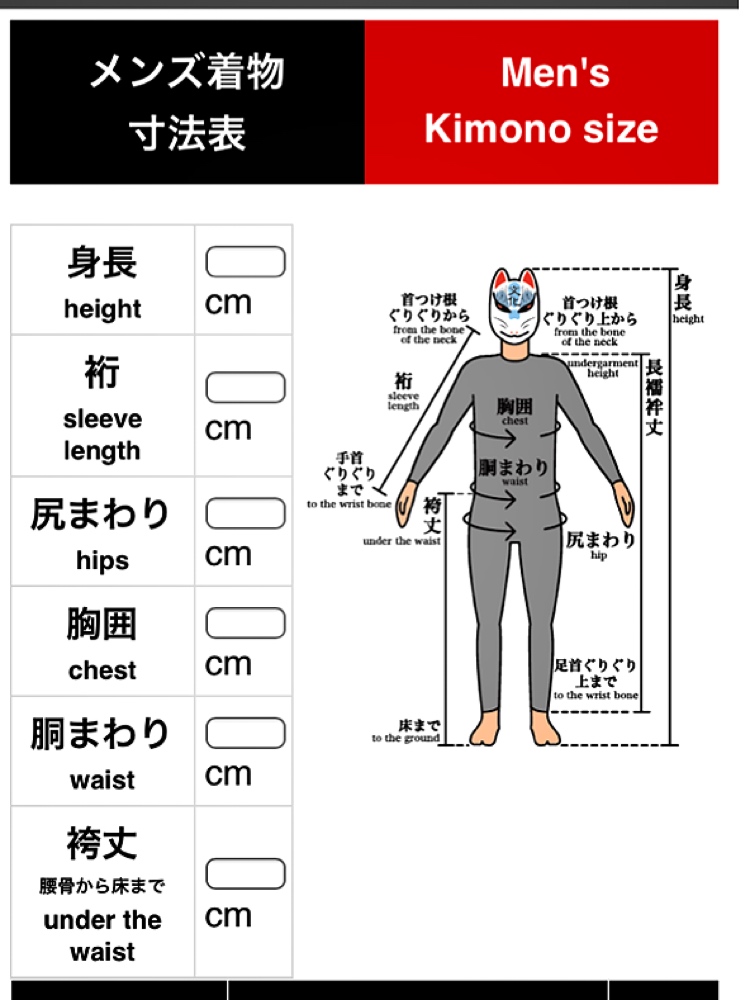
↑↑↑
上をクリックすると着物寸法表に飛びます。(着物、長襦袢、羽織、袴)
身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。
4.ポイント
結論
・袴を取り入れると、ドレス感がコントロール出来ます。
・シーンに合わせて使い分けると、着物ライフがより楽しくなります。
・普段のの袴の活用でより便利になります。
・袴の付け方をマスターしましょう。
以上、男の和服着物の袴(はかま)でした。
袴(はかま)と言うと、礼装系を思い描いてしまいがちですが
意外と普段からお召しになる方も多く、動きやすいと言います。
洋服で言う所のズボンなので、取り入れやすいかもしれないですね。
ライン@のアカウント変更しました!(2021年2月13日)

文化bunka◉着物モッズ【独創的な男の和服着物の研究家】